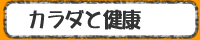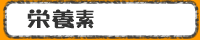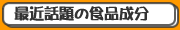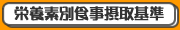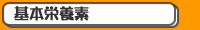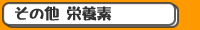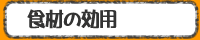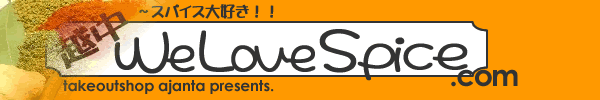健康で病気になりにくい体質作りと予防を提案しています。
特に、ガン予防と生活習慣病の予防には規則正しい生活と、栄養バランスの摂れた食事、
そして何より食事を家族・友人・恋人とおいしく楽しく摂ることが大切だと思います。
ここでは、日常生活で摂取しなければいけない基本栄養素と、最近話題の食品成分についていくつか紹介します。
丈夫な体質作りに参考にしてみてください。
〜最近話題の食品成分〜
イソフラボン
大豆の胚芽部分に含まれるポリフェノールの一種で、人体に入ると女性ホルモンのエストロゲンとして作用する物質です。
そのためイソフラボンは、エストロゲン減少によって起こる更年期障害の症状軽減に大変効果的な成分なのです。
例えば、エストロゲンは骨の代謝に深く関わっており、不足すると骨からカルシウムが排出されやすくなります。
更年期前後の女性はエストロゲンが不足して骨粗しょう症などになりやすいため、
積極的にイソフラボンを摂取することをお勧めします。
また、男性ホルモンの過剰な分泌が一因になっている高齢男性の前立腺がんにも、
女性ホルモンに近いイソフラボンの摂取が予防につながります。
イソフラボンは大豆や大豆製品で比較的手軽に摂取できます。
大豆を食べる習慣がある日本に生まれてきたのですから、それを生かして積極的に摂り入れたい成分です。
サポニン
植物全体に幅広く含まれる成分で、渋み、苦味などの主体です。
さまざまな種類がありますが、代表的なのが大豆サポニンです。
大豆サポニンは大豆の胚軸に多く含まれており、強い抗酸化作用があります。
また水と油の両方に溶ける性質があり、血管に付着した脂質を除去する働きや
血中コレステロールを低下させる効果があります。
大豆サポニンは体内脂質の代謝をよくすることから肥満防止に効果を発揮します。
さらに便通をよくして腸内環境を改善する働きもあるので、便秘解消や美肌効果も大いに期待でき、
大豆は美容・ダイエットにおける強力な味方となります。
クルクミン
カレー粉の黄色のもと、ターメリック(ウコン)に含まれる色素です。
優れた解毒作用や、抗酸化力があり、免疫力を高めガンの予防にも効果が期待されています。
胆汁の分泌を促進して、強力な解毒作用を発揮することで、肝臓の機能を高める働きもあります。
クルクミンはカレールウよりカレー粉のほうが多く含まれているので、できればカレー粉を使うことをお勧めします。
アントシアニン
ブルーベリーや赤ジソ、ブドウなどに含まれている赤紫色の色素で、目にいいことで知られる成分です。
自然着色料としても使われています。
目の網膜にあるロドプシンは光の刺激を受けると分解されさらに再合成されます。
しかしあまりに目を酷使するとロドプシンの再合成が追いつかなくなり、
目がチカチカしたり視界がかすむという症状がでてきます。
アントシアニンには、網膜の中のこのロドプシンの再合成をを活性化する作用があり、眼精疲労の回復や
視力の向上に有効なのです。また肝機能の回復・向上、血圧の上昇抑制にも効果があります。
アントシアニンの含有量は色の濃さに比例しますから、
ブルーベリーや赤ジソはなるべく色の濃いものを選ぶようにしましょう。
タウリン
魚介類に多く含まれる物質で、アミノ酸の一種です。
身体各部の機能を高める作用があり、スタミナドリンクの有効成分としてご存知の方も多いと思います。
タウリンには多くの効果がありますが、よく知られているのは高血圧の予防です。
タウリンには、脂肪を燃焼させ、全身各器官の機能を高める機能があります。
血圧を正常に保ち、心臓強化、貧血予防、血中コレステロールの抑制、糖尿病を予防します。
タウリンは魚介類、なかでも貝類やイカ、タコなどに多く含まれています。
高血圧改善効果を望むなら、野菜、キノコ類、海藻などの食物繊維と一緒に摂ることをお勧めします。
カプサイシン
カプサイシンは、トウガラシ特有の辛味成分で、
食欲増進、健胃、疲労回復、発汗や血行の促進といった効果があります。
カプサイシンは、中枢神経を刺激してアドレナリンの分泌をうながし、
エネルギー代謝をさかんにする働きがあります。
そのため肥満の予防にも役立つというわけです。
カプサイシンを摂るにはやはりトウガラシですが、一度に大量に取ると胃が荒れるので、
そこを気をつけて上手に使いましょう。
オメガ3系脂肪酸
オメガ3系脂肪酸は、脂肪酸を3つに分類したときの1つで、DHAやEPA、αーリノレン酸などがあります。
オメガ3系脂肪酸とオメガ6系脂肪酸は、エネルギーとして使われるだけでなく
体内でさまざまな生理作用を及ぼします。
リノール酸を含むオメガ6系脂肪酸はコレステロール値を低下させる効果がありますが、
摂り過ぎると肥満を招くだけでなく、悪玉コレステロールと一緒に
善玉コレステロールまでも減少させてしまいます。
それに対して、オメガ3系脂肪酸はこういったオメガ6系脂肪酸の作用を抑制する働きがあります。
また、オメガ3系脂肪酸のDHAにはカプサイシンやカフェインと同じように脂肪を燃やす酵素である
「燃焼リパーゼ」の働きを高めて、脂肪燃焼を促進しダイエットにも効果的です。
食の欧米化がすすみ、魚中心から肉中心の食生活にかわってDHAの摂取量は減っています。
オメガ3系もオメガ6系も健康を保つためには不可欠な脂肪酸です。
しかし現代の食生活ではオメガ6系脂肪酸が圧倒的に過剰で、
それを抑制するオメガ3系脂肪酸が顕著に摂れなくなっています。
オメガ3系脂肪酸を多く含む魚介類や、豆類、きのこ類などを積極的に摂るように心がけましょう。
ナットウキナーゼ
納豆特有の成分として注目されているのがナットウキナーゼです。
ナットウキナーゼは大豆を納豆菌で発酵させることによって生まれる酵素で、納豆以外の食品にはないものです。
このナットウキナーゼという酵素は血栓を溶かしだす作用があり、
一般の抗血栓薬にも匹敵するほどの強力な作用があります。
このため心筋梗塞や脳梗塞などを予防できます。
血栓は夜中から明け方にかけてできやすい傾向があるため、
納豆は朝食よりも夜食べたほうが血栓予防効果が期待できます。
クエン酸
柑橘類に多く含まれる酸で、人間の血液中に一定割合で含まれています。
クエン酸は糖の代謝を活発にし、疲労物質の乳酸を燃焼させてエネルギーにかえる働きがあり、
疲労回復に役立ちます。
また、クエン酸は体に吸収されにくい鉄やカルシウムなど脂溶性ミネラルを水溶性に変え吸収を良くしてくれます。
肩こり・腰痛の予防や、抗菌・抗ウイルス効果の高い健康成分です。
ビフィズス菌
ビフィズス菌は生後3〜4日目から腸内に増殖していき、大腸内の腐敗菌や病原微生物の増殖を抑制して
免疫機能を高めます。
ビフィズス菌には有害菌の増殖を抑えるだけでなく、老廃物の排泄を促進する働きもあり、
下痢や便秘の予防、老化防止、また肝臓障害を軽減する働きがあります。
ビフィズス菌は、加齢以外にもストレスや二日酔いによって減ります。
ヨーグルトやビフィズス菌のえさとなるオリゴ糖を摂るように心がけましょう。
栄養素別食事摂取基準(1日)
| 12〜14歳 | 18〜29歳 | 50〜69歳 | ||||
| 栄養素 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| カロリー | 2650kcal | 2300kcal | 2650kcal | 2050kcal | 2400kcal | 1950kcal |
| ビタミンB1 | 1.4mg | 1.2mg | 1.4mg | 1.1mg | 1.3mg | 1.0mg |
| ビタミンB2 | 1.6mg | 1.4mg | 1.6mg | 1.2mg | 1.4mg | 1.2mg |
| ナイアシン | 15mgNE | 13mgNE | 15mgNE | 12mgNE | 14mgNE | 9mgNE |
| ビタミンB6 | 1.4mg | 1.3mg | 1.4mg | 1.2mg | 1.4mg | 1.2mg |
| 葉酸 | 240μg | 240μg | 240μg | 240μg | 240μg | 240μg |
| ビタミンB12 | 2.4μg | 2.4μg | 2.4μg | 2.4μg | 2.4μg | 2.4μg |
| ビオチン | 45μg | 45μg | 45μg | 45μg | 4μg | 45μg |
| パントテン酸 | 7mg | 6mg | 6mg | 5mg | 6mg | 5mg |
| ビタミンC | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |
| ビタミンA | 700μgRE | 550μgRE | 750μgRE | 600μgRE | 700μgRE | 600μgRE |
| ビタミンE | 10mg | 8mg | 9mg | 8mg | 9mg | 8mg |
| ビタミンD | 4μg | 4μg | 5μg | 5μg | 5μg | 5μg |
| ビタミンK | 70μg | 65μg | 75μg | 60μg | 75μg | 65μg |
| マグネシウム | 300mg | 270mg | 340mg | 270mg | 350mg | 290mg |
| カルシウム | 900mg | 750mg | 650mg | 600mg | 600mg | 600mg |
| リン | 1350mg | 1100mg | 1050mg | 900mg | 1050mg | 900mg |
| 鉄 | 11.5mg | 9.5mg | 7.5mg | 9.5mg | 5.5mg | 9.0mg |
| 銅 | 0.8mg | 0.7mg | 0.8mg | 0.7mg | 0.8mg | 0.7mg |
| 亜鉛 | 9mg | 7mg | 9mg | 7mg | 9mg | 7mg |
| セレン | 30μg | 25μg | 30μg | 25μg | 30μg | 25μg |
| ヨウ素 | 140μg | 140μg | 150μg | 150μg | 150μg | 150μg |
| 食塩 | 1.5g | 1.5g | 1.5g | 1.5g | 1.5g | 1.5g |
基本栄養素
| 名称 | 主な作用 | 効用 | 欠乏症 | 多く含む食品 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | 糖質の代謝 | 精神安定 疲労回復 | 脚気 多発性神経炎 浮腫 心臓肥大 | 酵母 肉類 豆類 牛乳 緑黄色野菜 |
| ビタミンB2 | 代謝促進 成長促進 | 口内炎予防 脂質、糖質、たんぱく質の代謝促進 | 成長停止 口唇炎 口角炎 角膜炎 シビ・ガッチャキ症 | レバー 卵黄 胚芽 肉類 緑黄色野菜 |
| ビタミンB6 | たんぱく質・脂質の代謝 神経伝達の生成 | 脂肪肝の予防 月経前症候群を改善 | 皮膚炎 貧血 けいれん 湿疹 免疫力低下 | レバー 肉類 魚介類 卵 ニンニク |
| ビタミンB12 | 造血作用 | 悪性貧血の予防 | 悪性貧血 神経疾患 倦怠感 疲労感 痛み | レバー 肉類 魚介類 卵 チーズ |
| ナイアシン | 血行促進 | 胃腸障害の緩和 皮膚の健康を保つ | ペラグラ 口舌炎 胃腸病 皮膚炎 神経症状 | 酵母 肉類 豆類 牛乳 緑黄色野菜 |
| 葉酸 | 赤血球の生成 | 造血 口内炎の予防 成長促進 | 欠乏症の心配はない | 卵黄 牛乳 モロヘイヤ 菜花 |
| パントテン酸 | 副腎皮質ホルモンの合成 | 免疫力強化 抗ストレス | 副腎障害 | 肉類 魚介類 納豆 ヒラタケ モロヘイヤ |
| ビタミンC | 抗酸化作用 コラーゲン生成 インターフェロン生成、促進 | 抗がん 風邪予防 美肌効果 | 壊血病 皮下出血 骨形成不全 貧血 成長不全 歯肉色素沈着症 | 果物 ブロッコリー ほうれん草 イモ類 緑茶 |
| ビタミンA | 免疫機能維持 抗がん作用 | 皮膚や爪を丈夫にする 目の健康 動脈硬化予防 | 成長が止まる 骨、歯の発育が悪い 皮膚や粘膜の上皮の角化 | 肝油 バター チーズ 卵 緑黄色野菜 |
| ビタミンD | カルシウム、リンの吸収促進 | 丈夫な歯を作る 骨粗しょう症予防 | 小児ではクル病 成人では骨軟化症、骨粗しょう症 | いわし カツオ マグロ しらす干し キノコ類 |
| ビタミンE | 抗酸化作用 毛細血管の血行促進 性ホルモンの分泌促進 | 冷え症改善 美肌効果 更年期障害の軽減 | 位置感覚障害 | 穀物 はまち カボチャ アーモンド 植物性油脂 |
| ビタミンK | 血液凝固作用 | 骨の再石灰化 | 血液凝固時間がのびる 新生児の出血性疾患 | 明日葉 菜花 納豆 海藻類 緑黄色野菜 |
| コエンザイムQ10 | 細胞膜の抗酸化作用 | アンチエイジング効果 | 細胞膜保護作用低下 ミトコンドリア、ATP活性低下 | レバー モツ マグロ 肉類 大豆 |
| カルシウム | 歯、骨の組織形成 精神鎮静作用 | 精神安定 高血圧、動脈硬化予防 骨粗しょう症予防 筋肉の働きを良くする | 歯、骨が弱くなる 充分に成長しない 神経過敏になる | ホシエビ 煮干 ヨーグルト プロセスチーズ 豆腐 |
| リン | ナイアシンの吸収を助ける 骨を強化する作用 | 関節痛の緩和 成長促進 | 歯や骨が弱くなる 欠乏することはない | メバチマグロ ホシエビ プロセスチーズ そら豆 卵黄 |
| 鉄 | 酸素の運搬 造血作用 | 脳の働きを良くする 全身の機能を高める | 欠乏症の心配はない | ホシエビ 煮干 ヨーグルト プロセスチーズ 豆腐 |
| ナトリウム | 細胞の浸透圧維持 胃酸の分泌促進 | 熱中症予防 | 歯、骨が弱くなる 充分に成長しない 神経過敏になる | ホシエビ 煮干 ヨーグルト プロセスチーズ 豆腐 |
| カリウム | 血圧上昇を抑制 | むくみを解消 高血圧予防 過剰塩分を排泄 | 筋無力症またはマヒ状態になる 知覚がにぶくなり、反射が低下 | 海藻類 ほうれん草 セロリ サツマイモ アボガド |
| ヨウ素 | 代謝・発育促進 甲状腺ホルモンの成分となる | 甲状腺ホルモンの合成 エネルギー生産 | 甲状腺肥大をおこす 太りすぎる 疲れやすくなる 新陳代謝が鈍くなり、発育が止まる | 海藻類 イワシ サバ カツオ ブリ |
| マグネシウム | 体温、血圧維持 糖質、たんぱく質、脂質の代謝 筋肉の収縮 | 心疾患を予防 骨の代謝 | 欠陥が拡張して、過度に充血 神経が興奮しやすくなる | 魚介類 肉類 ほうれん草 バナナ 香辛料 |
| マンガン | 酵素を構成する 神経の刺激伝達 | 抗酸化作用 疲労回復 | 骨の発育低下 生殖能力の低下 生まれる子供が弱く、死亡率が高い 運動失調をおこす | 肉類 豆類 玄米 キウイフルーツ 干ししいたけ |
| 銅 | ヘモグロビン合成 | 血管壁強化 髪や皮膚の色を正常に保つ | 貧血 骨折・変形を起こす | レバー すじこ ホシエビ ココア カシューナッツ |
| コバルト | 骨髄の造血作用 | 貧血予防 | 貧血 | レバー 魚介類 肉類 モヤシ 納豆 |
| 塩素 | 消化促進 pHバランスの調整 | ペプシンの活性化 | 浸透圧に影響 | 海藻類 |
| 亜鉛 | DNA、たんぱく質の合成 細胞の新生 | 味覚を正常に保つ 生殖機能向上 脱毛予防 | 充分に成長しない 皮膚障害 味覚障害 | 魚介類 肉類 玄米 豆類 木の実 |
| セレン | 抗酸化作用 抗がん作用 | がん予防 老化防止 | 充分に成長しない | ウルメイワシ アワビ ワラビ ネギ ミルクチョコレート |
| クロム | 糖質と脂質の代謝 | 糖尿病予防 高血圧予防 | 耐糖能が低下する 昏迷 | アサリ ひじき 牛肉 マイイワシ ザーサイ |
| 硫黄 | 胆汁分泌促進作用 | 骨や皮膚をつくる 有害ミネラルの蓄積を防ぐ | 皮膚炎 関節が弱くなる 解毒能力低下 | 魚介類 肉類 卵 牛乳 チーズ |
| フッ素 | 歯の再石灰化促進 細菌抑制 | 歯のエナメル質の強化 虫歯菌の抑制 | 虫歯 骨多孔病 | 煮干 シバエビ 緑茶 番茶 抹茶 |
| モリブデン | 尿酸代謝 | 鉄欠乏性貧血予防 食道がん予防 | 成長遅延 | 豆類 緑葉類 ワカメ バナナ レバー |
その他栄養素
必須アミノ酸必須脂肪酸
食物繊維
必須アミノ酸
たんぱく質の栄養価は、それを構成するアミノ酸の種類と量によって優劣が決まります。アミノ酸からつくられるたんぱく質は、体内で筋肉や臓器などの構成部分、酵素やホルモンの材料になります。
また、神経伝達物質の成分にもなり、脳の働きを活性化したり、免疫機能を高めるなどの働きもしています。
アミノ酸のうち、イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジンの9種類は人体でほとんど合成されないうえに、人体にとって必要不可欠なものです。よって、これら9種類のアミノ酸を必須アミノ酸と呼び、必ず食物から摂らなければなりません。
必須アミノ酸ではありませんが、アミノ酸の1種であるアルギニンは発育期の子供には不可欠であるとされています。
| 和名 | 解説 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| トリプトファン | トリプトファンは牛乳から発見された必須アミノ酸の1つで、精神安定、鎮静、催眠効果があります。過剰摂取は肝臓に負担がかかるので摂りすぎに注意しましょう。 | 鶏レバー 小麦胚芽 そば プロセスチーズ 高野豆腐 |
| フェニールアラニン | フェニールアラニンは脳と神経で信号を伝達する働きをします。精神を高揚させる働きがあるため、抗うつ剤として利用されています。 | 小麦胚芽 そば 小麦の強力粉 高野豆腐 納豆 |
| リジン | リジンは体のたんぱく質の組み立てになくてはならない必須アミノ酸で、たんぱく質の吸収を促進させ、疲労回復、成長促進に役立ちます。ホルモンを産出して、受精率を高めます。不足すると、肝機能が低下してコレステロール値が上昇するとされています。 | サワラ サバ 小麦胚芽 そば 納豆 |
| ロイシン | ロイシンは肝機能を高めて、筋肉を強化するのに効果的で、疲れやすい人に適しています。幅広く食品に含まれているため、不足することはありません。 | 牛肉 レバー トウモロコシ 牛乳 チーズ |
| イソロイシン | イソロイシンは体の成長を促進し、血管拡張、肝機能向上、筋力強化の作用があります。 | サケ 鶏肉 牛肉 牛乳 チーズ |
| バリン | 血液中の窒素バランスを調整する働きがあり、たんぱく質が代謝されるときに利用されます。 | 牛肉 レバー 牛乳 チーズ |
| スレオニン | 食事から摂ったたんぱく質が代謝するときに必要とされ、成長と新陳代謝を促します。肝臓に脂肪が蓄積するのを防ぎ、脂肪肝を予防します。 | 鶏肉 卵 スキムミルク さつまいも ゼラチン |
| ヒスチジン | 子供は体内で合成できないため、食品から摂取する必要があります。ストレスの軽減、性的エネルギーの向上の働きもあります。 | 鶏肉 牛肉 ハム チーズ ドライミルク |
| メチオニン | 硫黄を含む含流アミノ酸で、体の中のヒスタミン血中濃度を下げる働きがあり、蕁麻疹やかゆみを起こすとき、これを軽減します。抗うつ剤としての即効性も認められています。 | 牛肉 羊肉 レバー 牛乳 全粒小麦 |
必須脂肪酸
脂肪酸は三大栄養素の1つである脂質の主成分で炭素・水・酸素から構成され、結合形態で二重結合を持たない飽和脂肪酸、二重結合を持つ不飽和脂肪酸に分かれます。
飽和脂肪酸は不飽和脂肪酸に比べて融点が高く、二重結合を多く持つ脂肪酸ほど融点が低くなります。
動物性油脂(バター、ラードなど)は飽和脂肪酸が多いため、室温でも固体状の「脂」です。
それに対して植物性油脂(大豆油、ゴマ油など)は不飽和脂肪酸が多いため、液体状の「油」です。
飽和脂肪酸はヒトの体内で凝固しやすく、過剰に取ると血液の粘度が増して動脈硬化になりやすくなります。
不飽和脂肪酸は、悪玉(LDL)コレステロールの抑制や、過酸化脂質の発生を予防する効果があります。
| 和名 | 解説 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| リノール酸 | 体内で生成されない必須脂肪酸で、コレステロール値や中性脂肪値を下げる作用があります。摂り過ぎると肥満を招き、また酸化しやすい傾向があります。 | サフラワー油 リンゴ マッシュルーム ブナシメジ ヒラタケ |
| α-リノレン酸 | 多価不飽和脂肪酸で、食品から摂取しなければならない必須脂肪酸です。悪玉コレステロールを抑えるほか、アレルギー症状を改善し、摂り過ぎによる過剰症はありません。 | 菜種油 大豆油 鮎 キウイ カキ |
| アラキドン酸 | 必須脂肪酸の一つで肉、卵、魚などに含まれ、血液サラサラ効果、肝機能の向上、アレルギー症状の予防、コレステロール値の低下などの効果があります。過剰摂取は、動脈硬化、高血圧、慢性の炎症、アレルギー性湿疹、アトピー性皮膚炎などの症状を引き起こします。 | アワビ サザエ 豚レバー 鶏ササミ 豚ヒレ |
| オレイン酸 | 一価不飽和脂肪酸で、善玉コレステロールを減らさずに、悪玉コレステロールのみ減らす効果があります。ほかの脂肪酸に比べて酸化しにくく、過酸化脂質を生じにくいのが特徴です。 | ひまわり油 オリーブ油 メカジキ 牛肉 豚肉 |
| DHA | 多価不飽和脂肪酸で、魚の脂肪に含まれています。悪玉LDLコレステロールや中性脂肪を減少させ、高血圧、動脈硬化、脳卒中などを予防したりします。脳をはじめとする神経組織に多く含まれ、脳や神経の発達や機能を高めます。過剰摂取すると、出血が止まりにくくなります。 | スルメイカ クロカジキ 春鰹 メジマグロ シーラ |
| EPA | 血液の粘度を低下させ、血栓症を予防し、動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中、高血圧といった生活習慣病を防ぎます。うつ病や統合失調症にも効果があります。 | バイガイ マコガレイ スケソウダラ ホッケ メバル |
| γ-リノレン酸 | 多価不飽和脂肪酸で、通常の食品にはさほど含まれておらず、体内でリノール酸から変換することで摂取します。生活習慣病の予防、アレルギーや月経痛の改善に効果があるとされています。 | ヨーグルト ワカメ コンブ なまこ 加工乳 |
食物繊維
トローウェルが食物繊維をヒトの消化酵素で分解されない植物性の多糖および、リグニンと考え、多くの人々に認められて今日に至っています。 アメリカの食品医薬品局(FDA)では、ヒトの消化酵素に抵抗する食物中の植物性物質と定められており、 我が国でも食物繊維の示す機能性重視の立場から、ヒトの消化酵素で分解されない食物中の総体と定義されています。食物繊維は、可溶性食物繊維(SDF)と不溶性食物繊維(IDF)とに大別され、合計を総食物繊維(TDF)としています。 SDFの中でゲルを作りやすいものは胆汁酸の排泄を促進するので、血中コレステロールの上昇抑制作用が認められています。そのほかに食品のグリセミックインデックスを規定する因子として、体内のエネルギー利用にも影響を与えています。 IDFを中心とした吸着による排泄促進作用、またTDF摂取量の増加により腸内容物の移動促進作用の結果として刺激緩和などによる大腸ガン発症や大腸憩室の抑制作用など、いくつかの作用をあげることができます。
このように食物繊維は生活習慣病の予防因子の1つとして重要であり、摂取量の増加は糖尿病や高脂血症の予防・治療などにも広く利用されています。
| 和名 | 解説 | 多く含む食品 |
|---|---|---|
| 不溶性食物繊維(IDF) | ||
| キチン・キトサン | 髪の甲羅や海老の殻に存在する多糖類の一種で、消化管内で胆汁酸を吸着して血中コレステロールを低下させます。体内に取り込まれた食品添加物や、環境汚染物質などの有害物質を排泄させる働きもあります。癌、肝炎、肝臓病、糖尿病、高脂血症、高血圧、アレルギー性疾患、不眠症、神経痛、リウマリ、肩こり、視力障害、骨粗しょう症などあらゆる症状に改善の効果があります。最近では、人工皮膚の原料として脚光を浴びています。 | カニの甲羅 海老の殻 イカの軟骨 チーズ キノコ類 |
| セルロース ヘミセルロース | 穀類の外皮に多く含まれる食物繊維で、有害物質の排泄や大腸がんの予防に効果があります。 | ゴボウ 小麦ふすま 玄米 大豆 きなこ |
| ペクチン | 果物に豊富に含まれる食物繊維で、糖尿病や、高脂血症、動脈硬化、胆石などを予防します。 | キャベツ 大根 みかん オレンジ リンゴ |
| グルカン | きのこ類に含まれるβグルカンは抗がん作用がある成分として古くから知られています。中でも、サルノコシカケ科、シメジ科、ハラタケ科のキノコに含まれるβD-グルカンは強力な腫瘍抑制効果が認められています。 | 干ししいたけ キクラゲ シメジ ヒラタケ アガリスク茸 |
| リグニン | 化学的変化を受けにくく、腸内の善玉菌を増やす働きがあるのが特徴です。 | ふすま イチゴ ラズベリー 豆類 ココア |
| 水溶性食物繊維(SDF) | ||
| フコイダン | 海藻に含まれる多糖類で、抗がん作用、肝機能向上、抗アレルギー、血圧抑制の効果があります。 | コンブ ワカメ もずく めかぶ |
| グルコマンナン | コンニャクに含まれる食物繊維で、水を吸収しやすい性質からダイエット食品に多く含まれています。 | グルコマンナン 添加食品 |
| アルギニン酸 | 海藻類の細胞間物質に含まれているヌメリ成分で、高血圧予防や、血中コレステロール抑制、血糖値の上昇抑制、動脈硬化予防などの作用があります。 | コンブ ワカメ モズク めかぶ |
| ポリデキストロース | 日本では、1983年に食品添加物として許可され、加工食品に添加されています。整腸作用や、血中コレステロール、血糖値を下げる働きがあり、発がん性物質を排泄させる作用もあります。 | ポリデキストロース 添加食品 |
| コンドロイチン硫酸 | 人間の体内で、たんぱく質結びつき、コンドロムコタンパクとして皮膚や血管壁、軟骨、靭帯、関節、眼球、角膜、粘液、各臓器に分布しています。体細胞組織に潤いを与え、栄養吸収や、新陳代謝を促進する働きがあります。成長期には、体内で生成されますが、加齢とともに生産量が減り、老人性のシワや乾燥肌の原因とあることもあります。コエンドロイチン硫酸は、ヌルヌルした食感の食品に多く含まれます。 | フカヒレ オクラ やまいも ワカメ ナメコ |
Copylight 2006-2009"www.welovespice.com" All Right Reserved.